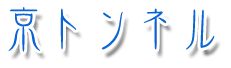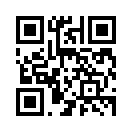2007年07月13日
絶筆
この間の週末に兵庫県立美術館に行って日本近代画家の「絶筆」展を見に行きました。

「絶筆」とは
①書くことをやめること。筆を断つこと。
②生前に最後に書いた文章や絵など。 (辞書抜粋)
今回は②の意味です。主催者の挨拶文に
『死を前にした画家は最後に何を見、そして何を表現するのでしょう・・・(中略)
「絶筆」の定義は様々です。未完作品など厳密に画家が生涯最後に手を入れたものを「絶筆」とする事もあれば、最後の展覧会出品作や完成作を「絶筆」としている事もあります。
さらには、画家の没後、関係者によって晩年作の中から意図的につくられた「絶筆」もあります。
しかし今回は、あえて「絶筆」を定義づけたり分類したりすることなく、画家達が死の直前に描いた作品をできるだけ多くあつめる事で「絶筆」の多様性を浮き上がらせたいと考えています。
(以下省略)』
今回の展覧会はとてもとても心打たれました。
画家が最後に見たもの、それは「海」であったり「月と太陽」であったり、「女」、「花」など・・・
病に苦しみながら描きあげ、最後のサインは手が震えてかけず、友人が描いたり・・・、
入院中の病院の屋上からみたビル景色、死を予感させるような黒い背景の絵、はたまた柔らかい光を浴びた婦人を描き、充足感に満ちた絵など・・・・。
自分的に目を伏せたくなるような絵もありました。
筆のうねりや色使いを感慨深く間近に鑑賞しながら考えました。
今まで数え切れない位色んな展覧会を見に行きましたが画家の人生の最後を深く考える事は
ありませんでした。
素人目から見て大雑把な絵でもその画家が今まで何枚も何枚も描き続けて
辿り着いた結果の絵はとても意味のあるもので画家の人生を表しているんですよね。
今私が有名画家とそっくりの絵を描けたとしてもその絵に対し説得力も何もないですよね。
何かを形にして表現したらそれはその人の人生がすごく表れると思うし
見る者の受け取り方も様々ですが、1番は心が入ってないといけないですね。
まして死が迫っている事をわかっていた画家はどんな思いで描いていたんでしょう。
この絶筆展ではそんな事を改めて考えました。
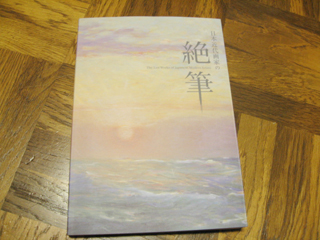

「絶筆」とは
①書くことをやめること。筆を断つこと。
②生前に最後に書いた文章や絵など。 (辞書抜粋)
今回は②の意味です。主催者の挨拶文に
『死を前にした画家は最後に何を見、そして何を表現するのでしょう・・・(中略)
「絶筆」の定義は様々です。未完作品など厳密に画家が生涯最後に手を入れたものを「絶筆」とする事もあれば、最後の展覧会出品作や完成作を「絶筆」としている事もあります。
さらには、画家の没後、関係者によって晩年作の中から意図的につくられた「絶筆」もあります。
しかし今回は、あえて「絶筆」を定義づけたり分類したりすることなく、画家達が死の直前に描いた作品をできるだけ多くあつめる事で「絶筆」の多様性を浮き上がらせたいと考えています。
(以下省略)』
今回の展覧会はとてもとても心打たれました。
画家が最後に見たもの、それは「海」であったり「月と太陽」であったり、「女」、「花」など・・・
病に苦しみながら描きあげ、最後のサインは手が震えてかけず、友人が描いたり・・・、
入院中の病院の屋上からみたビル景色、死を予感させるような黒い背景の絵、はたまた柔らかい光を浴びた婦人を描き、充足感に満ちた絵など・・・・。
自分的に目を伏せたくなるような絵もありました。
筆のうねりや色使いを感慨深く間近に鑑賞しながら考えました。
今まで数え切れない位色んな展覧会を見に行きましたが画家の人生の最後を深く考える事は
ありませんでした。
素人目から見て大雑把な絵でもその画家が今まで何枚も何枚も描き続けて
辿り着いた結果の絵はとても意味のあるもので画家の人生を表しているんですよね。
今私が有名画家とそっくりの絵を描けたとしてもその絵に対し説得力も何もないですよね。
何かを形にして表現したらそれはその人の人生がすごく表れると思うし
見る者の受け取り方も様々ですが、1番は心が入ってないといけないですね。
まして死が迫っている事をわかっていた画家はどんな思いで描いていたんでしょう。
この絶筆展ではそんな事を改めて考えました。
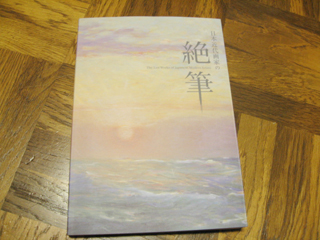
Posted by Dora at 21:00│Comments(3)
この記事へのコメント
どのような絵かわかりませんが、
あなたの目を伏せさせてしまうことが出来た画家は
本望ではないでしょうか。
展覧会が意図し、またあなたが感じられた様に、
直面する死が単一のものでないこと、死が「訪れる」のではなく、
もともと持っていたものが姿をあらわすゆえにその人なりの
死となること。
死すらその人の一部であること。
そんなことを考えました。
死がテーマだけに暗いですね、このコメント。(ごめんなさい。)
突然お邪魔してしまいました。
ではでは。失礼いたします。
あなたの目を伏せさせてしまうことが出来た画家は
本望ではないでしょうか。
展覧会が意図し、またあなたが感じられた様に、
直面する死が単一のものでないこと、死が「訪れる」のではなく、
もともと持っていたものが姿をあらわすゆえにその人なりの
死となること。
死すらその人の一部であること。
そんなことを考えました。
死がテーマだけに暗いですね、このコメント。(ごめんなさい。)
突然お邪魔してしまいました。
ではでは。失礼いたします。
Posted by +0 atelier at 2007年07月14日 10:37
+0 atelier さん、コメントありがとうございます!
あなたがおっしゃった『死が「訪れる」のではなく、
もともと持っていたものが姿をあらわすゆえにその人なりの
死となること。死すらその人の一部であること。』
・・・・そうかもしれないです。誰にとっても死は自分の一部。
死が姿をあらわした絵は直面しきれず私にはまだなんというか
痛い感じでした。
これからまだまだ夢をふくらませていく最中に急逝した画家もいて
それを思うとなんでもできる今この日々が幸せですね。
私も頑張って夢を追いかけたいです。
また是非いらっしゃって下さい(~_~)
あなたがおっしゃった『死が「訪れる」のではなく、
もともと持っていたものが姿をあらわすゆえにその人なりの
死となること。死すらその人の一部であること。』
・・・・そうかもしれないです。誰にとっても死は自分の一部。
死が姿をあらわした絵は直面しきれず私にはまだなんというか
痛い感じでした。
これからまだまだ夢をふくらませていく最中に急逝した画家もいて
それを思うとなんでもできる今この日々が幸せですね。
私も頑張って夢を追いかけたいです。
また是非いらっしゃって下さい(~_~)
Posted by Dora at 2007年07月14日 14:22
うん、たしかに幸せ。
また来ます!
ではでは。
また来ます!
ではでは。
Posted by +0 atelier at 2007年07月15日 11:07
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。